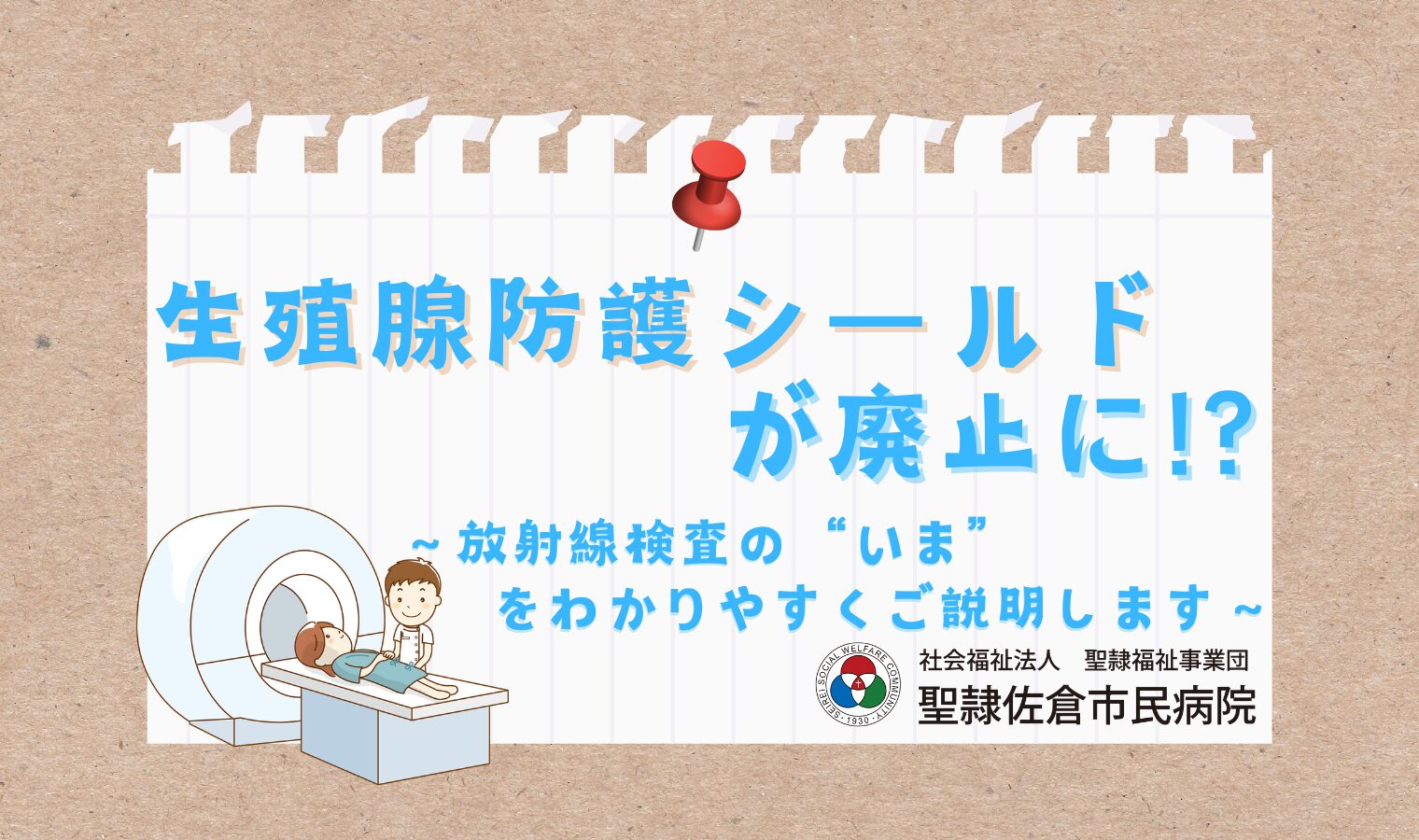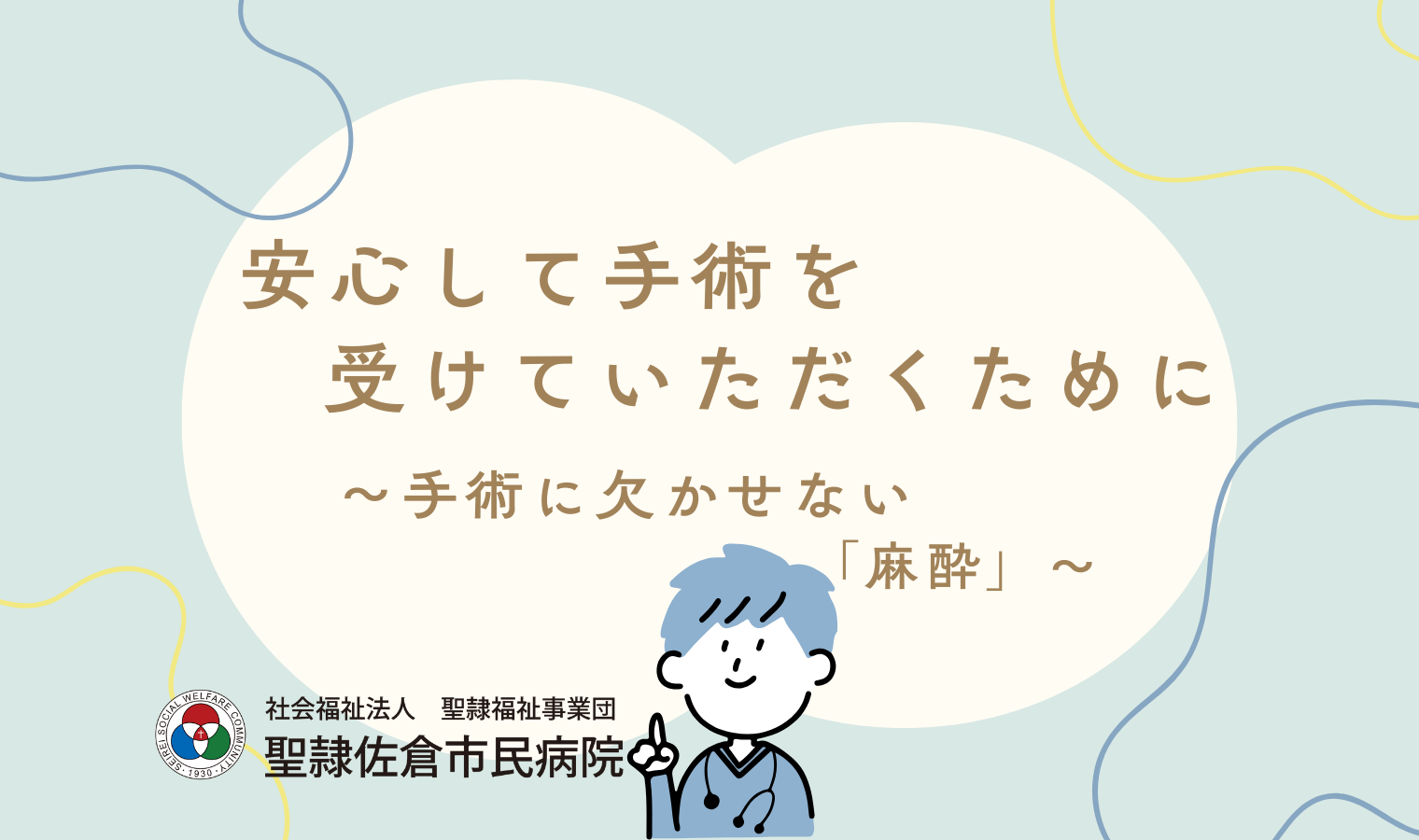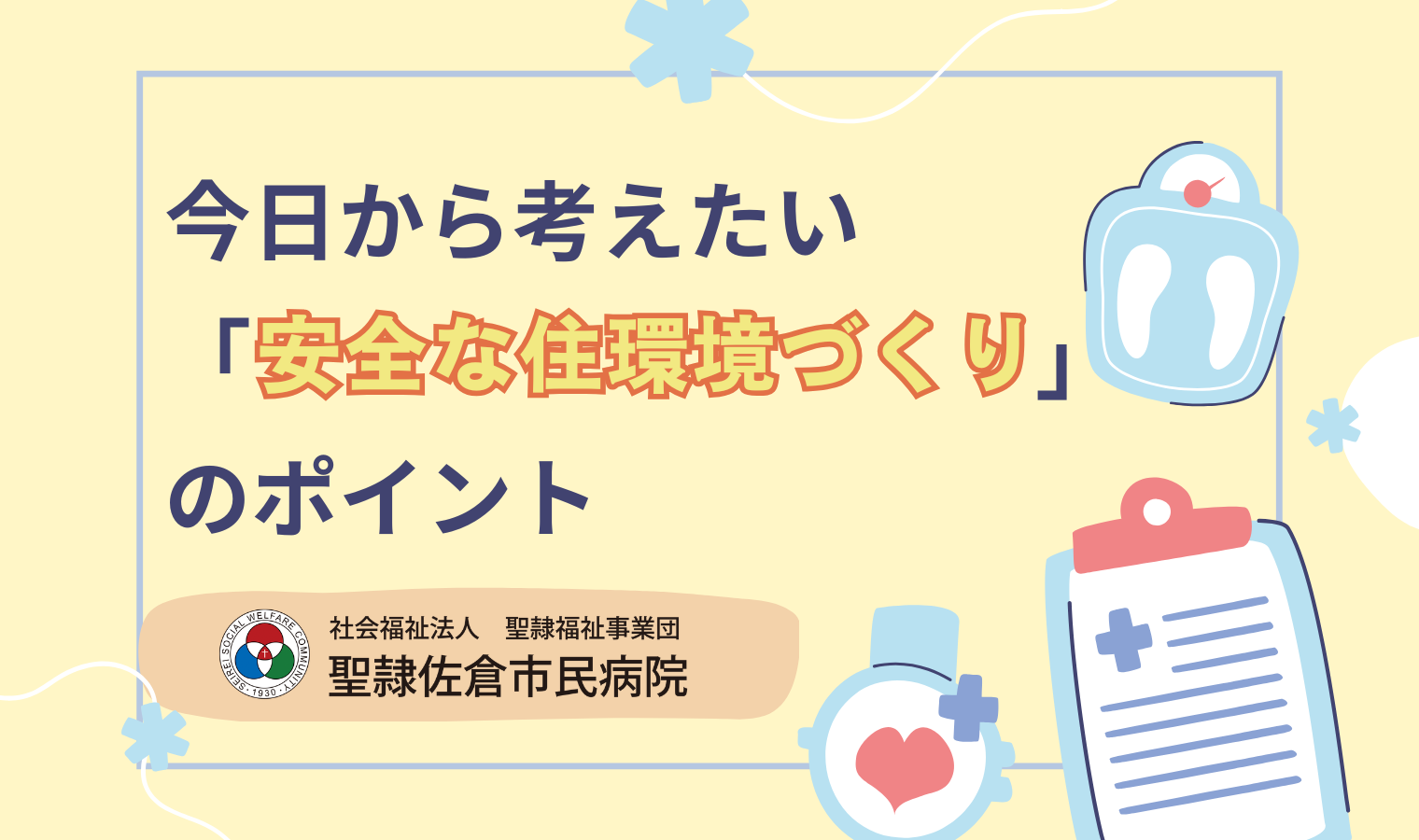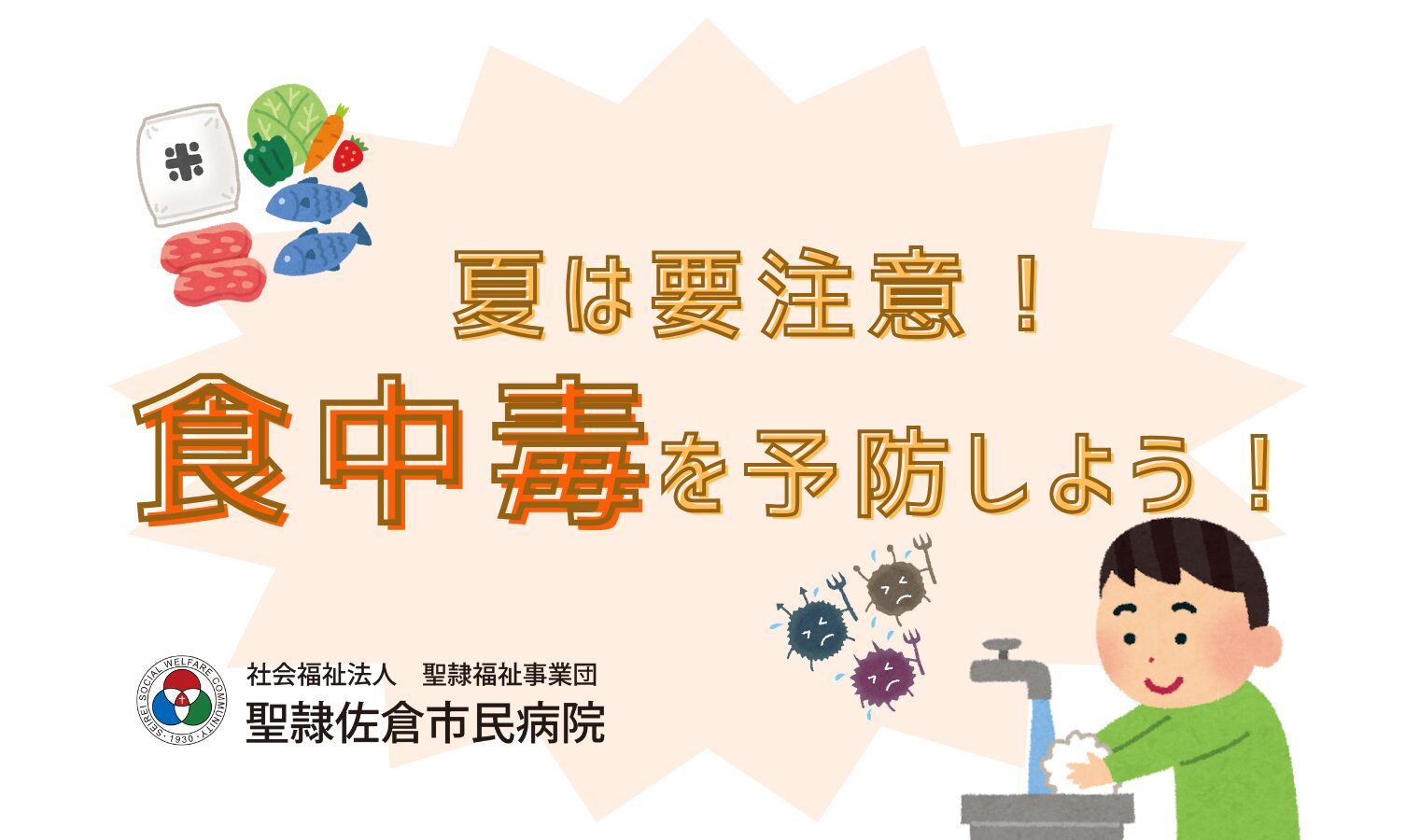
夏は要注意!食中毒を予防しよう!
投稿日 2025.07.24
気温・湿度の高くなる夏は細菌による食中毒が発生しやすい季節です。
今回は、食中毒の原因・予防・6つのポイントについてご紹介します。
食中毒の原因は・・・
食中毒の原因となる細菌やウイルス、有毒物質がついた食べ物を食べることにより、下痢、腹痛、発熱、吐き気などの症状が出ます。 細菌による食中毒は気温が高く、細菌が増えやすい6月から9月ごろに発生しやすくなります。

食中毒予防の3原則に気をつけましょう!
食中毒を起こす細菌やウイルスが食品についているかどうかは、見た目や味やにおいではわかりません。食中毒を予防するには「つけない」「増やさない」「やっつける」の3つが重要です。
つけない
口に入る食材に細菌が「つかない」ように手洗いや調理器具の洗浄・消毒や食品の洗浄を行いましょう。
増やさない
食品に付いた細菌は時間とともに増殖し、30~40℃が最も増殖しやすい温度帯となります。増やさないために、調理後は早めに食べるようにしましょう。また、すぐに食べない場合は常温放置せず、粗熱が取れたら冷蔵庫や冷凍庫で保存しましょう。
やっつける
細菌は熱に弱いものも多く、食材の中心まで熱を通すことで死滅します。中心温度が75℃以上・1分以上の加熱が効果的です。焼く、煮る、蒸す、揚げる、ゆでる、炒める、電子レンジでの加熱を行いましょう。

ご家庭でもできる食中毒を防ぐ6つのポイント!
食中毒は、誰にでも起こる可能性があります。毎日の買い物や調理、食品の保存の中で少し意識するだけで、しっかり予防することができます。
ご家庭でもすぐに実践できる「6つのポイント」をご紹介します。
①買い物
・肉・魚・野菜などの生鮮食品はなるべく新鮮な物を選び、食品に表示されている「消費期限」、「賞味期限」をよく確認しましょう。
・肉や魚の汁・水分が他の食品に付かないよう、ビニール袋にそれぞれ分けて包みましょう。
・冷蔵・冷凍の温度管理が必要な食品は、買い物の後半にし購入後は早めに帰り長時間持ち歩かないようにしましょう。また、保冷バックや保冷剤・氷を上手に活用しましょう。
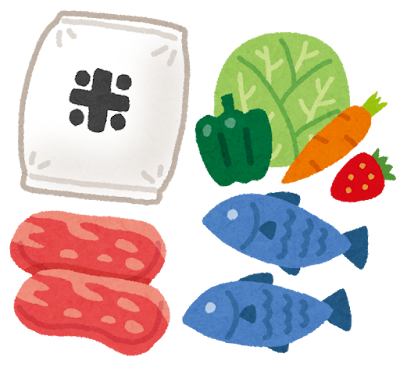
②食品の保存
・冷蔵・冷凍食品は帰宅後すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。(冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下が目安)
・冷蔵庫の中で肉や魚の汁・水分が他の食品に付かないよう食品別に容器・ビニール袋へ入れましょう。
・冷蔵庫や冷凍庫は詰めすぎると空気の流れが悪くなり冷えにくく温度にムラができやすくなるため、中身は7割程度を目安にし注意しましょう。
③下準備
・作業の前や肉・魚を触ったあとは必ず石鹸で手を洗いしましょう。
・タオルや布巾は清潔な物と交換し、不要な物は片付け、ゴミはこまめに捨てるなど台所を清潔に保ちましょう。
・生肉や生魚を切った包丁・まな板はよく洗ってから熱湯をかけ、消毒してから他の食品に使いましょう。
・ラップで包まれている野菜やカット野菜も調理前に洗いましょう。
・冷凍食品の解凍は使う量だけとし、常温ではなく冷蔵庫内や電子レンジを使いましょう。

④調理
・調理前に手を洗うのはもちろん、調理器具やキッチンも清潔に保ちましょう。
・肉や魚の汁・水分が生で食べる食品や調理済みの食品など他の食品に付かないよう離れたところで作業しましょう。
・加熱する食品は中心温度が75度以上1分間以上を目安に十分加熱しましょう。また、電子レンジ加熱では、均一に加熱されるように時々混ぜるのがおすすめです。
・調理を中断するときは常温放置せず、冷蔵庫で保管し、再調理の際に十分に加熱しましょう。
⑤食事
・食事の前に石鹸で手を洗いしましょう。
・清潔な調理器具と食器に盛り付け、食品は室温・常温に長時間置かないようにしましょう。
・温かい料理は温かいうちに(65℃以上)、冷たい料理は冷たいうちに(10℃以下)が目安です。
⑥残った食品の保管
・食べ残しを扱う前にも、必ず手を洗いましょう。
・残った食品は早く冷めるように浅い容器に小分けして保存し、温め直すときは十分加熱しましょう。
・少しでも怪しい・不安だと思ったら無理に口にせず捨てましょう。

食中毒予防の3原則、食中毒を防ぐ6つのポイントを活用し、食中毒にならないようにしましょう。
管理栄養士秦野