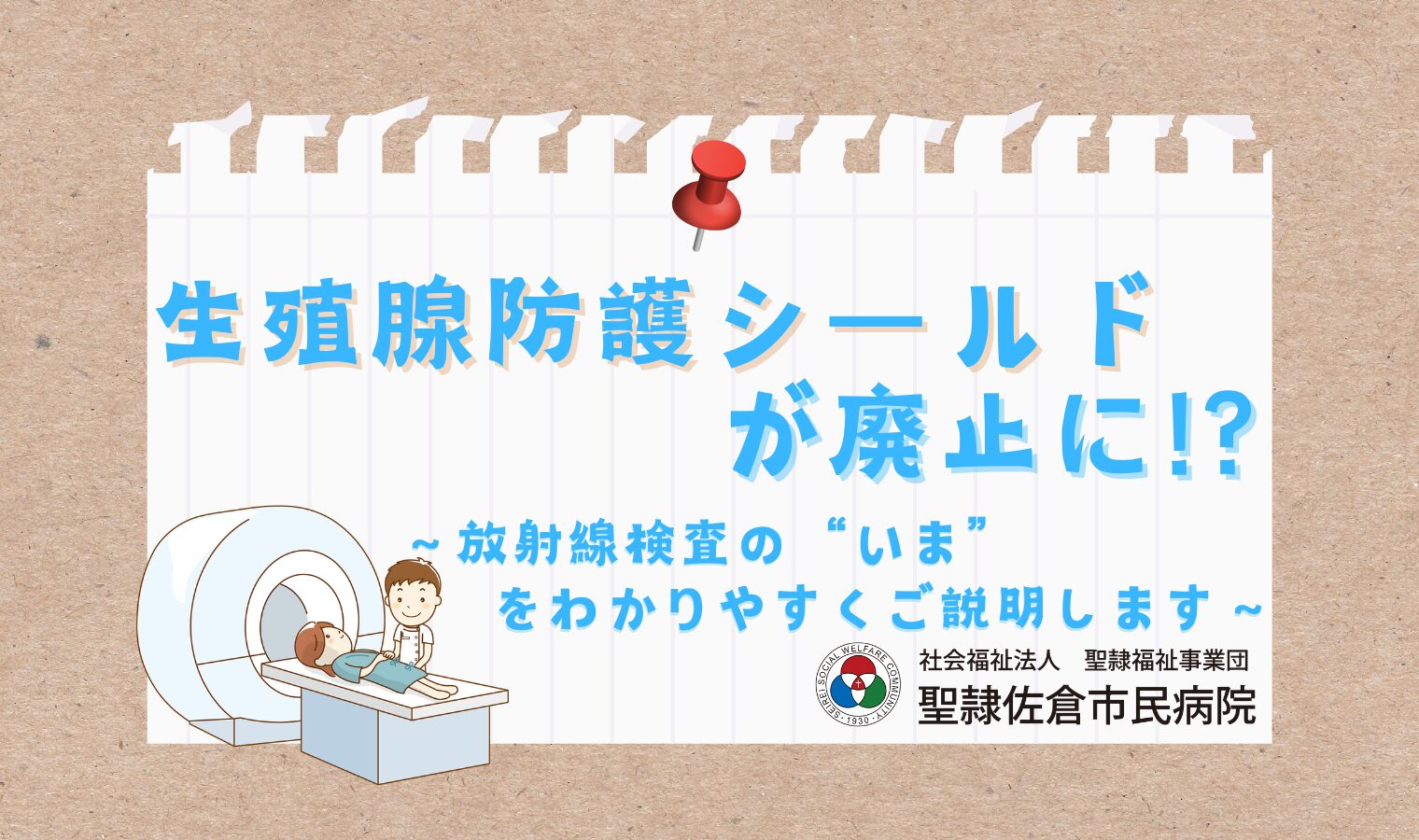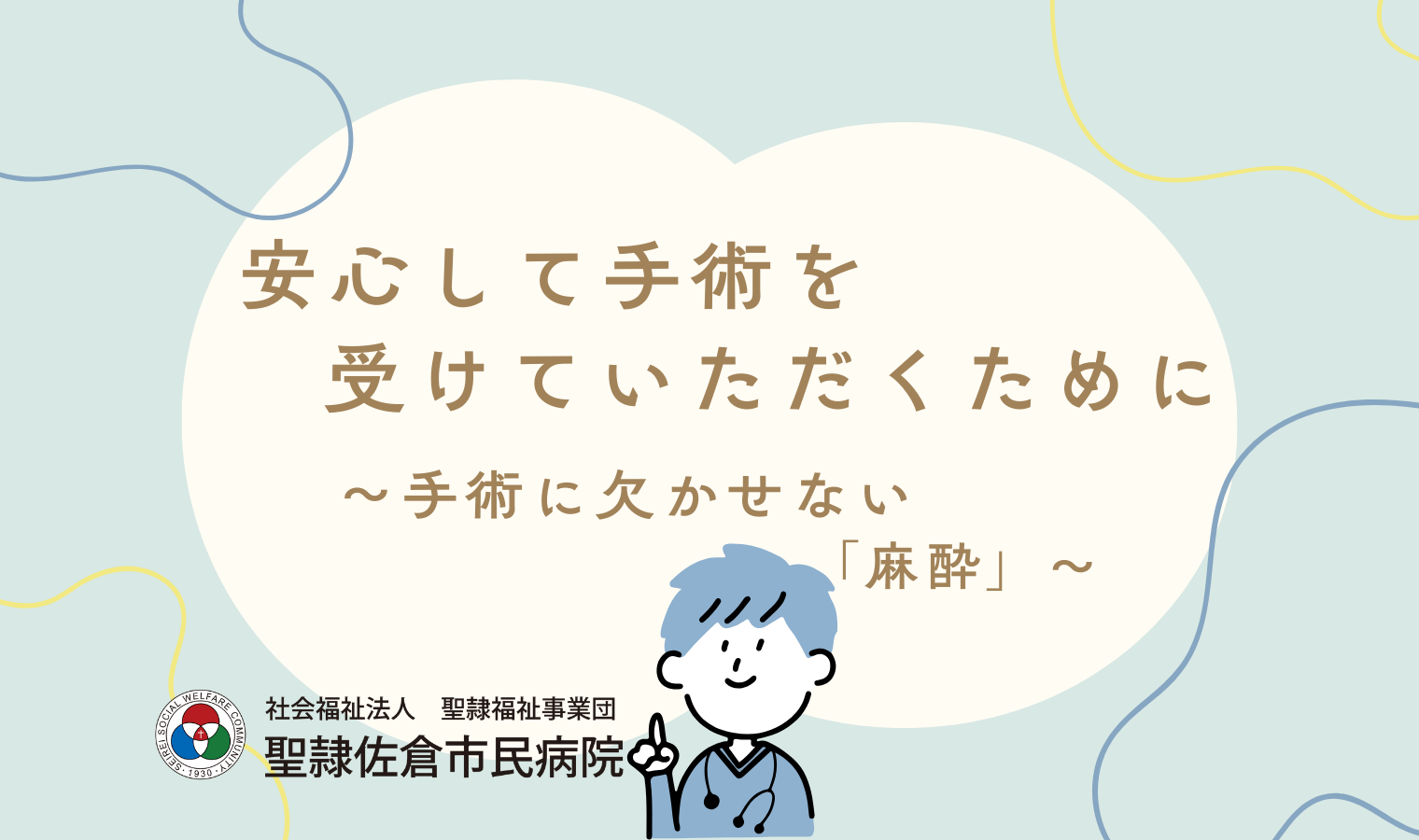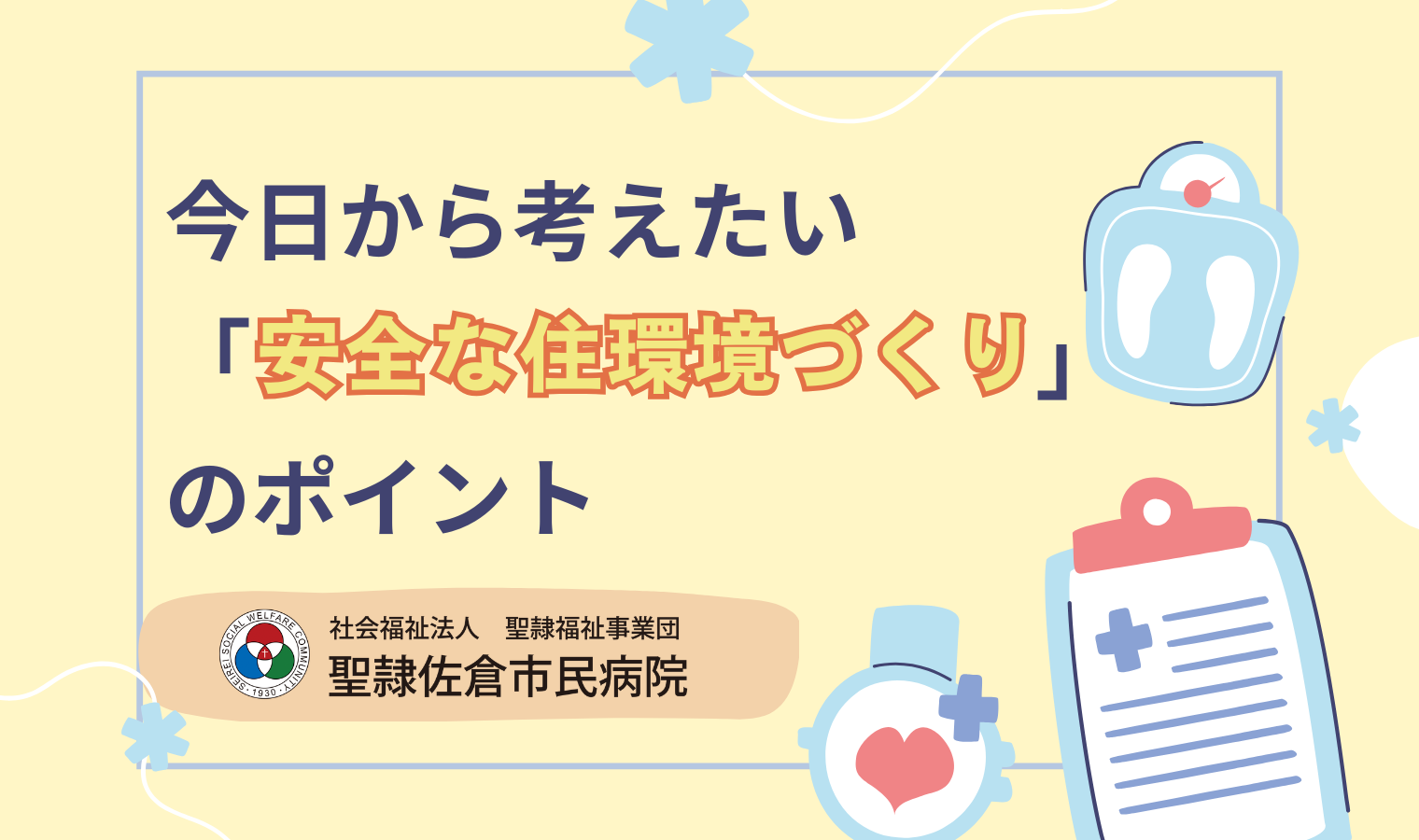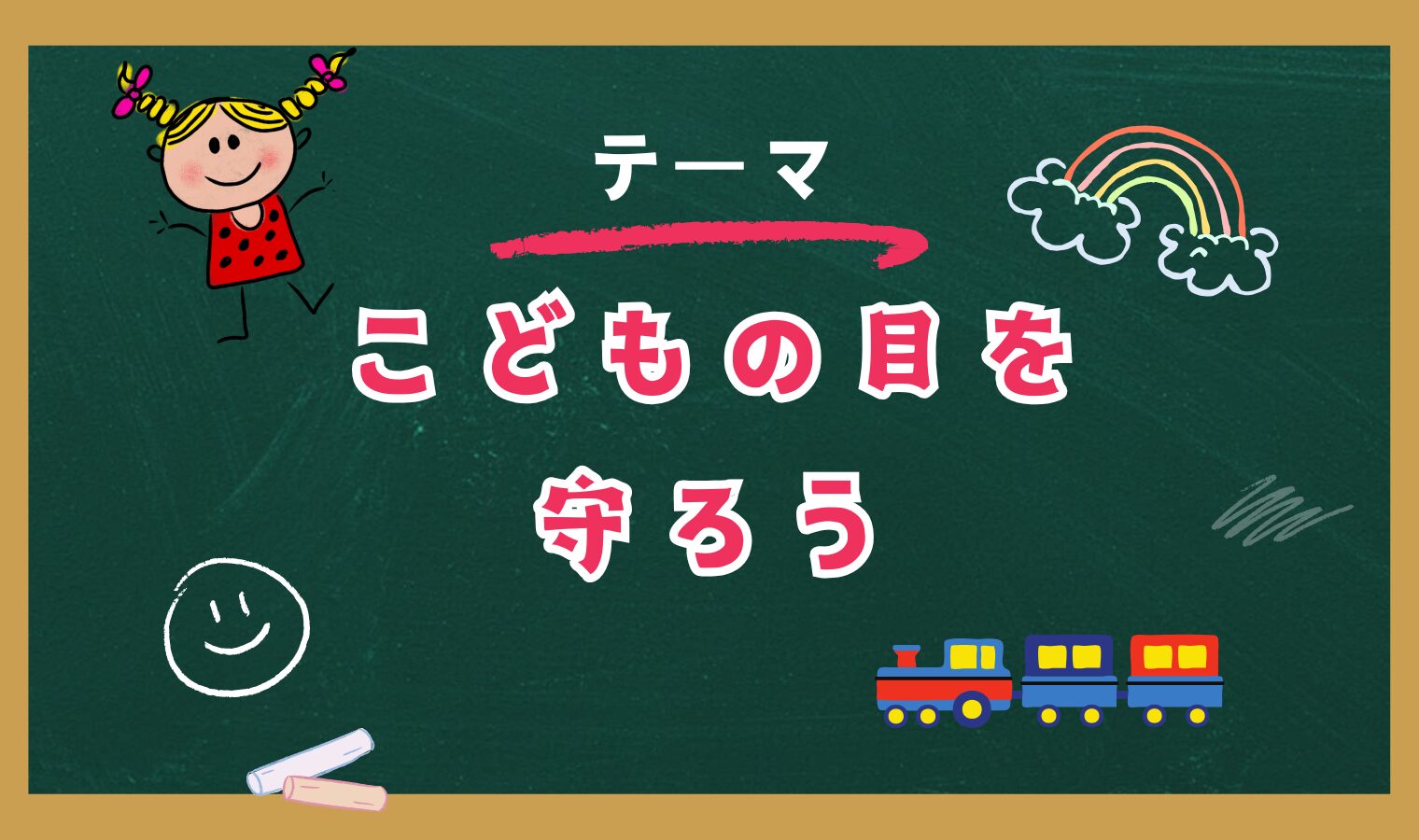
こどもの目を守ろう
投稿日 2025.04.03
人生で初めて視力検査をしたのがいつか、覚えていますか?
多くの人が三歳児健診だと思います。大人は直感的に答えられる検査でも、こどもにとっては理解が難しいことはたくさんあります。
お子様が小さい視標まで見えていないときに「検査が難しいだけかな」「普段見えづらそうにしているわけじゃないから」と軽く考える前に、保護者の方に知っておいてほしいことがあります。
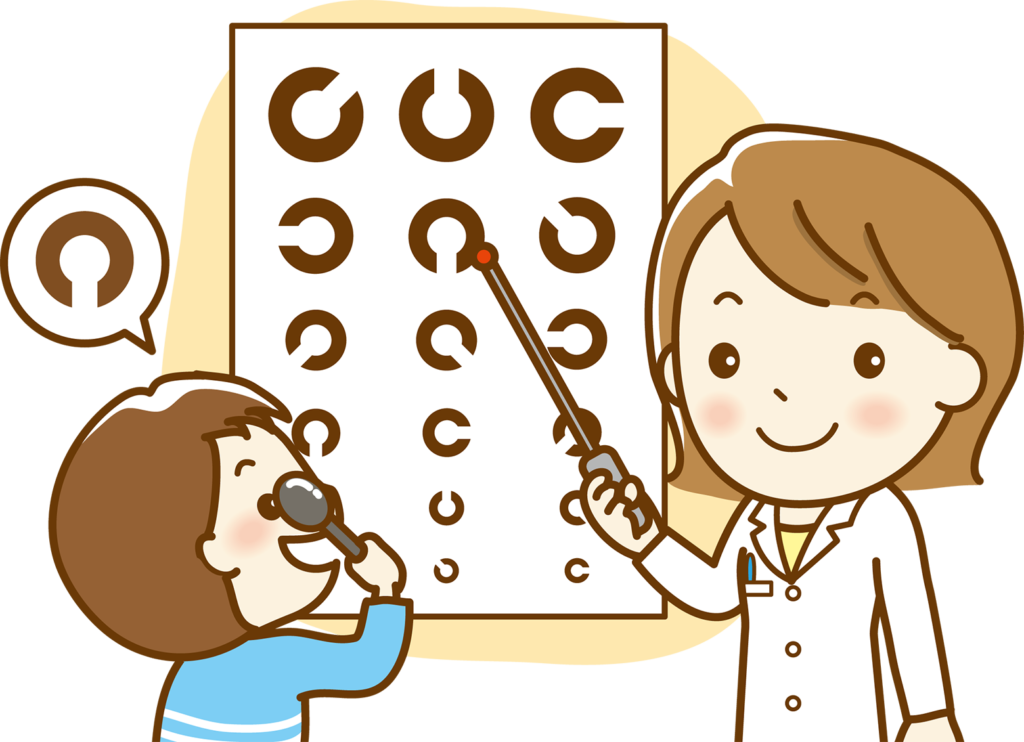
こどもの視力検査は特に、理解が難しく上手に検査ができないだけなのか、本当に見えていないのか、見極めることがとても大切なのです。
3歳時点での視力検査の重要性
視力は生まれてから徐々に発達していき、生後18か月付近で最も感受性が高くなります。その後感受性は下降し、視力の発達期間は6~8歳までと言われています。
この期間までに視力が1.0や1.2まで育たないと、その後いくら眼鏡やコンタクトレンズを合わせても視力が上がることはありません。
言い換えると、8歳頃までに0.6しか視力が育たなかった子は、大人になったときの最高視力も0.6までしか出ないのです。
この状態を“弱視“と言います。


弱視治療について
視力の発達がゆっくりであるとわかった場合、どのように治療していくのでしょうか。
様々な方法がありますが、どの治療方針でも前提として「屈折矯正」が必要です。これはしっかりと眼に合わせた度数の眼鏡をかけるということです。はっきりと見える世界を作ってあげることで視力は成長していきます。
眼鏡をかけることに抵抗がある子は少なくありません。ですが、治療に必要な眼鏡をかけなかったことで弱視のまま大人になってしまう将来を避けるためにも、こども達が眼鏡をかけやすい環境をまわりの大人がつくってあげましょう。
本人が気に入るフレームを一緒に選び、「似合ってるね」「かわいい/かっこいいね!」というまわりからの声かけが眼鏡を自発的にかけてくれるモチベーションになるのです。
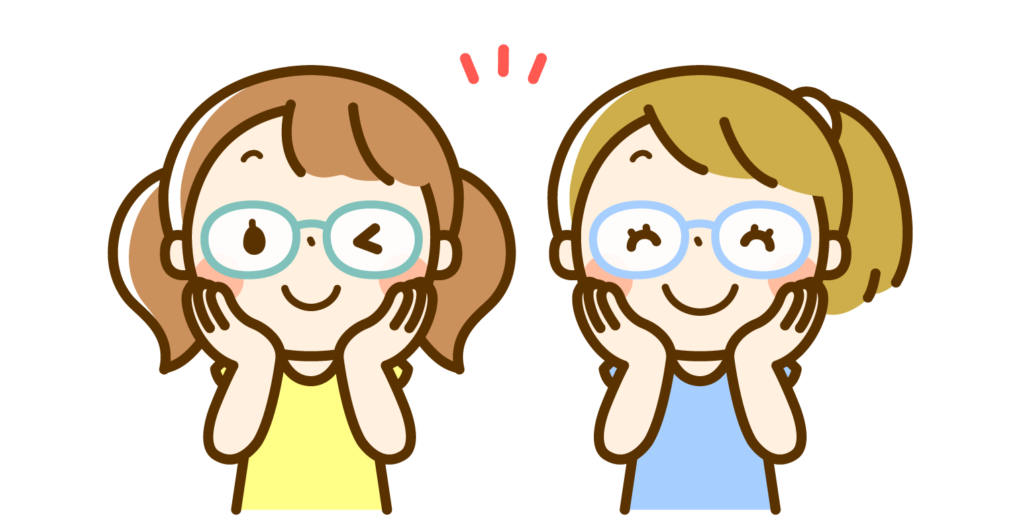
もちろん、3歳児健診時の普段と異なる環境や、理解が難しくて上手にできなかっただけで本当は視力が育っていることも多くあります。
その場合でも、少しずつ検査に慣れていき、良好な視力が出ることを確認するまで一緒に成長を見守りますので一度眼科に受診することをお勧めします。

出典 公益社団法人 日本視能訓練士協会
診療科により、受付時間・休診日が異なります。
ご受診される方はホームページにてご確認の上ご来院ください。